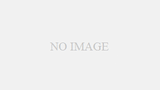近年、クラフトビールが注目を集めています。有名なものはスーパーやコンビニでも手に入るようになりました。
クラフトビールの銘柄数は年々増加していて、醸造所の数は、2025年現在で800とも900とも言われています。ここ10年ほどの間には、大手ビールメーカーも参入し、市場は活況を呈しています。
このクラフトビールは飲んでおいしいだけでなく、地方とその農業を救う切り札にもなり得るのです。
クラフトビールの歴史は地ビールにあり
そもそもクラフトビールとはどういったものなのでしょうか?
クラフトビールに明確な定義は存在しません。
しかし、元をたどると1994年に誕生した地ビールに行き着くという説があります。
地ビールの定義は「1994 年の規制緩和を受けて全国各地に誕生し,地域に密着した小規模醸造のビールで,多様性を持つ新たなビール文化の切っ掛けとなった」(全国地ビール醸造者協議会)とされており、黄金井康巳氏の研究では、「我が国で地ビール産業が確立されたことは,新たな嗜好の多様性に応えたビール分野として,我が国に“クラフトビール”の道を切り開いた先駆けであることに間違いはありません」と述べられています。
地ビール=クラフトビールとするには無理があるかもしれませんが、地ビールなくして現在のクラフトビールブームはなかったと言えるでしょう。
また黄金井氏によれば、アメリカのアソシエーションはクラフトビールについて、「①小規模であること。②独立していること。③伝統的であること」と定義しています。これを日本に当てはめると、多くのクラフトビールは、①と②は満たしていますが、③には疑問が残ります。
日本のクラフトビールは独自に進化していると言えるでしょう。

クラフトビールはどこで作られてる?
酒類のラベルのデザインなどを行っている「きた産業株式会社」の調査によると、日本国内には2024年末時点で900以上の醸造所があるとされており、なんと47の都道府県すべてにクラフトビールの醸造所があることが明らかになっています。
そしてこのうち最も多いのは東京都で123か所、次いで神奈川県の61か所、北海道の44か所と続きます。さらに長野県では40か所、大阪府でも39か所で作られています。
ホップは、比較的冷涼な地域で栽培されることが多いことから、日本国内では東日本以北でのよく栽培されています。そうしたことから、クラフトビールの醸造所の数も、どちらかと言えば西日本よりも東日本の方が多いという特徴があります。
中でも、ビールの原料となるホップの栽培が盛んな北海道や、ビール作りに欠かせない水がきれいなイメージを持つ長野県で多くのクラフトビールが作られることは想像に難くないですが、意外にも東京都や神奈川県といった大都市で作られることも多いのです。
ちなみに、ホップの生産で有名な遠野市を擁する岩手県には17の醸造所があります。
おおむね、消費量が多い大都市圏と、地方では原料となるホップの生産が盛んな地域で、多くのクラフトビールが生産されていることがわかります。
農業の6次産業化との深い関わり
クラフトビールは、その醸造所の数から見てもわかるように、ホップの生産、すなわち農業との関りが深いのです。
国は現在、地域資源の活用・価値の創出という観点から、農林漁業の6次産業化を進めています。
6次産業化とは、一次産業(生産)と二次産業(加工)、それに三次産業(流通・販売)を掛け合わせた産業を指します。
地方で生産されるホップを使って、地方でクラフトビールを醸造することは、まさしくこの6次産業に当てはまるのです。
「ホップを生産する農家×クラフトビールを作る醸造所×流通・販売」という図式が成り立つからです。
この6次産業化は、離農者問題や耕作放棄地の問題に悩む、地方の農業を救う可能性を秘めると同時に、地域活性化にも貢献するのです。

特色あるクラフトビールの作り方
醸造家の方々は、オリジナルのビールを作ろうと奮闘しています。
ビールの原材料は主に大麦、ホップ、水、酵母です。しかし、ほかにもその土地で収穫される野菜、例えば梅、オレンジピールといった果物のほか、トウモロコシやジャガイモ、サツマイモ、さらにはコメを副原料として用いたビールもあります。こうした副原料を用いることで特色ある味や風味が生まれます。
ビールの作り方は、①大麦からモルト(麦芽)を作る、②仕込み、③発酵・貯酒・熟成という手順で作られますが、その手法によっても味や色が変わります。例えば、モルト作る際、乾燥や焙煎を行いますが、その温度によって色が変わりますし、発酵させる期間によっても味が変わります。
醸造家の皆さんが、ビールを作り上げるまでのストーリーを楽しめるのもクラフトビールならではです。原料を生産する農家との関係性や、なぜその土地にブルワリーを開業したのかなど、大手メーカーではできない楽しみ方でもあります。
素材選びから生産方法、生産に至るストーリーまで、千差万別。
地方の醸造所=ローカルブルワリーが果たす役割は大きいと言えそうです。
知るほど楽しいクラフト○○
ちなみに、酒類の6次産業化はビールだけにとどまりません。
ワインは「ワインツーリズム」という言葉があるほど、すでに観光資源として認識されています。各地のワイナリーでは、その土地で栽培されたブドウを用いて、オリジナルのワインが生産されています。
日本酒も、全国各地に酒造メーカーや酒蔵があり、その土地の名物を肴に楽しめるほか、お土産として購入するなど、地域の活性化につながっています
近年は「クラフトウイスキー」もブームになっていますし、最近では「クラフトジン」も注目を集めています。特に、クラフトウイスキーには人気があり入手困難となっている銘柄もあるほどです。

その土地ならではの農産物を活用したアルコール飲料は、私たちにお酒を味わうことの楽しみを教えてくれます。
農業×お酒は無限の可能性を持っていると言えるでしょう。
少々値が張ったり、希少価値が高いものは入手が困難なものもありますが、たまの贅沢にクラフトビールで乾杯するのもいいかもしれません。
また、地方の特色あるブルワリーを巡る旅も、お酒好きの方にはたまらないでしょう。それぞれの楽しみ方を見つけ味わいたいものです。
参考
- 全国醸造所リスト
https://kitasangyo.com/beer/MAP.html - 農林水産省ホームページ「農林漁業の6次産業化」
https://www.maff.go.jp/j/nousin/inobe/6jika/index.html - 黄金井康巳(2018)地ビールの将来展望ー地ビールからクラフトビールへ.日本醸造協会誌113(4)