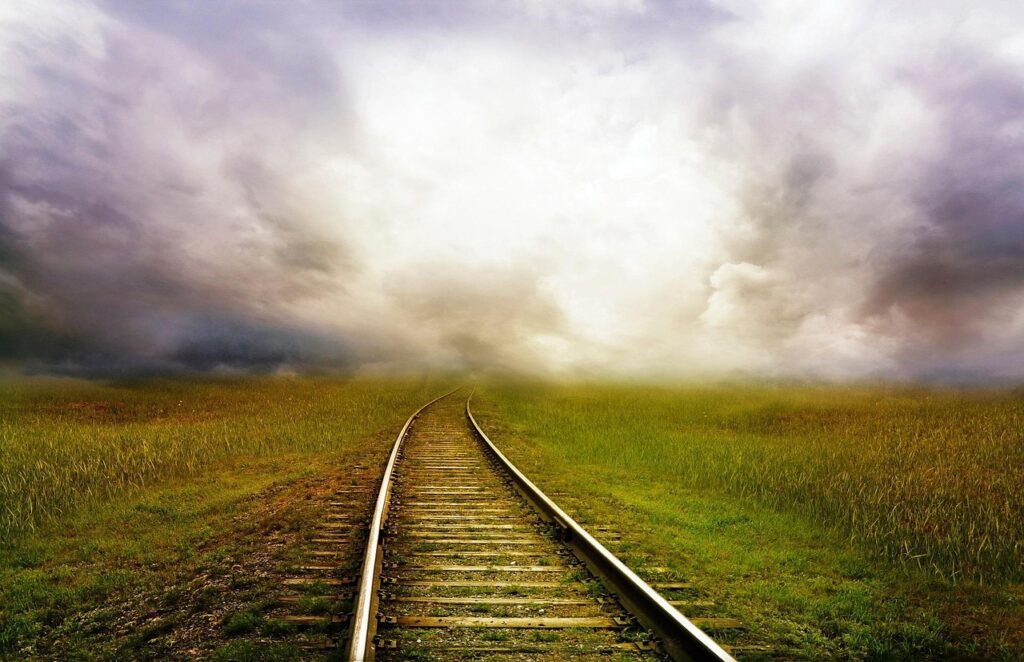
全国には廃線となった路線が数多くあります。国鉄時代には「特定地方交通線」が選定され、そのほとんどが第三セクター鉄道へ移行したり、廃線となりバスにより代替されたりしました。
2000年代に入っても、2000~2008年の9年間に25路線、574kmの路線が廃止されているうえ、2020年度には146.6km、2021年度にも116kmの路線が廃線となっています。
時代の流れとともに鉄道が不要になり、結果として廃線となることには仕方ない部分もあります。加えて、今後も地方の人口減少による利用客の減少、豪雨や災害の発生などにより、その数は増えていくことが予想されます。
そこで、その線路跡をどう活用していくのかという問題が発生するのです。
そうした廃線跡の活用方法として候補に挙がるのがサイクリングロードへの転用です。
こうした「鉄道の廃線跡を再利用した散歩道を、サイクリストや歩行者が移動やレクリエーションの手段として活用する旅行形態」のことをレールトレイルといい、発祥のアメリカから世界各国へ広がり、日本でも見られるようになりました(藤井,2023)。
中でも代表的な事例が茨城県にあります。
廃線跡をサイクリングロードに―リンリンロードの事例
茨城県南東部に位置するつくば市。人口26万を超える、日本を代表する研究学園都市です。
この街には現在、つくばエクスプレス(通称TX)が走っており、東京の秋葉原との間を最速45分で結んでいます。TXの開業は2005年。今年で開業20周年を迎え、首都圏屈指の混雑路線として知られています。
しかし、遡ること数十年。TXが開業するよりも昔。1つのローカル鉄道が走っていました。その名を「筑波鉄道筑波線」(以下筑波線)と言います。
筑波線は1918年に土浦(土浦市)~岩瀬(現・桜川市)間が全通しました。しかし、モータリゼーションなどの影響を受け、利用客が減少、1987年に廃止されてしまいます。
その筑波線の廃線跡を一部活用したサイクリングロードが「つくば霞ケ浦りんりんロード」です。
つくば霞ケ浦りんりんロードは筑波線廃止後の1992年から自転車道としての整備が進められ、2002年に筑波線の全線にあたる桜川市(JR岩瀬駅前)~土浦市(JR土浦駅前)間約36kmのサイクリングロードが全通しました。
さらに2016年には土浦市から霞ケ浦周辺を経て、潮来市へと至るサイクリングロードと合わせて整備され、全長約180kmの長大なサイクリングロードが完成しています。
つくば霞ケ浦りんりんロードのルートはおおむね平坦で初心者にも走りやすいことが特長です。
沿道の景色もバラエティに富んでおり、全線通して筑波山を見つつ関東平野北部の田園地帯を進みますが、途中の真壁地区には歴史的な街並みが残っており、情緒あふれる景観が楽しめます。
都市景観は土浦市内のほか、つくば市域でも遠くに市街地の建物群を目にすることができます。
このサイクリングロードの中核を成すのはつくば市に隣接する土浦市です。
JR常磐線を利用することで東京都心からのアクセスに優れており、サイクリングの玄関口として機能していることがうかがえます。
土浦駅には、隣接してサイクリストをターゲットとしたホテルが開館したほか、駐輪場を併設したサイクルショップやメンテナンスコーナー、情報発信コーナーやシャワールームを備えた「りんりんスクエア土浦」があり、サイクリストに優しい環境が整っています。
土浦駅前以外にも、ルート沿いには筑波線の駅跡を中心として休憩スペースやサポートステーションが点在しているほか、拠点となる休憩所にはトイレはもちろん、駐車場が併設されており、自家用車でのアクセスも容易です。
上記のような先進的な環境整備や景観の良さ、コースの充実度合いなどから、2019年には国が創設した「ナショナルサイクルルート」にも選定されています。
また、茨城県の資料やホームページによると、こうした取り組みにより、2015年度には約39,000人だった利用者が、2023年度には約125,000人まで増加しています。

多くの利用者がいるものの課題も
観光面でみるとりんりんロードの事例は、大成功と言って差し支えないでしょう。
これは自治体や関係事業者の取り組みもさることながら、人口が多い首都圏に位置していること、また東京からのアクセスが容易なことも大きく影響しているといえそうです。
一方で、茨城県は大都市圏からの近さゆえ、日帰り客が多いことが課題であるとしています。宿泊客が少ないということは宿泊業だけでなく、付随する飲食業界などへの経済効果が小さいことを意味します。
こうした課題はりんりんロードだけではなく、大都市近郊の観光地に共通しているでしょう。より大きい経済効果を得るための工夫も必要です。
先に書いたように、鉄道の廃線跡を用いたサイクリングロードは全国各地に存在します。道幅や鉄道特有の緩やかな勾配・曲線部など、廃線跡の活用法として適していることがその要因と考えられます。
しかし数が多いということは、それだけライバルが多くなるということです。観光振興につなげるためには特色や魅力を創出し、差別化を図る取り組みが求められます。

地元住民の日常的な利用も必要
リンリンロードの事例が示すように、サイクルツーリズム(自転車観光)による誘客を図るためには、関連施設の整備はもちろん重要ですが、立地やアクセス、コースの特性など、環境や地理的要因によっても大きく左右されるのが現実です。
しかし、鉄道の廃線跡が大都市近郊にあるとは限りません。むしろ今後は地方鉄道の廃線が多くなると考えられます。なかなか都合よく廃線跡があるとは限らないのです。
その中で、地方はどのような集客戦略を立案し、ほかのサイクリングロードと差別化を図り、より大きい経済効果を生むかは、地域ごとに議論が必要です。
廃線となった線路跡をサイクリングロードへ転用する場合、線路跡が鉄道会社から自治体へ払い下げ、もしくは無償譲渡が行われ、そのあとに自治体が整備を行います。自治体が整備するので一部には税金が投入されることは想像に難くありません。廃線跡をサイクリングロードとして活用する場合は、こうしたケースが目立ちます。
自治体が税金を投入して整備することを考慮すると、観光振興だけでなく、地域住民が利用しやすいサイクリングロードを整備することも必要だと考えられます。
特に地方では住民の高齢化の進行が顕著です。高齢者の健康寿命を延ばすためには日常的な運動が欠かせません。
サイクリングは日常的な運動にも適しています。自治体はサイクリングロードの造成と同時に、地域住民への自転車の購入支援やメンテンナンス施設の整備を行うことで、地域住民のサイクリングロード活用を図ることができるのではないでしょうか。
観光だけでなく、住民の健康維持のために廃線跡が活用されるとなれば、それは素敵なことです。
地域住民も観光客も、高齢者から子どもまで多くの人々が安心して走れる、廃線跡がそんなサイクリングロードへと進化することを願ってやみません。

参考
- 藤井秀登(2023)レール・トレイルにおけるヘリテージの文化的解釈とツーリズム―サイクル・ツーリズムの視点から―.第38回日本観光研究学会全国大会学術論文集
- 茨城県ホームページ「つくば霞ヶ浦りんりんロードのR5年度の利用者」https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/sports/cycling/r5-riyousya.html
- 国土交通省資料「近年廃止された鉄道路線」https://www.mlit.go.jp/common/000021485.pdf
- 三ツ木丈浩(2022)土浦市におけるサイクリングツーリズムについて 観光情報発信を中心に.埼玉女子短期大学研究紀要 第45号


